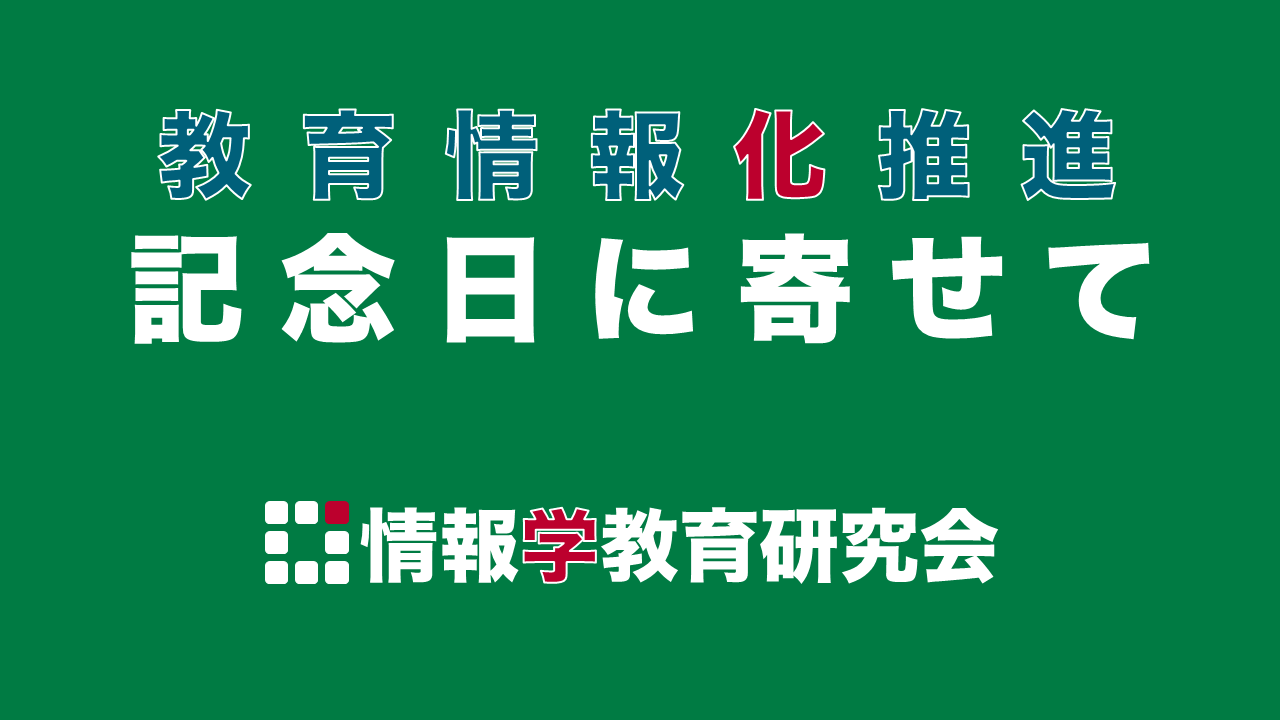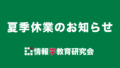情報学教育研究会は,2020年4月1日に教育情報化推進研究会と統合し,従来の情報学教育の研究開発・支援に加え,教育の情報化についてもその対象となりました。2010年7月29日は教育情報化推進研究会の創立日であったことから,情報学教育研究会では,7月29日を教育情報化推進記念日と位置づけています。
この記念日にあたり,情報学教育研究会 代表 横山成彦のメッセージを掲載いたします。
代表 メッセージ
情報学教育研究会は,毎年7月29日を「教育情報化推進記念日」と定めています。これは,2010年7月29日に教育情報化推進研究会が創設されたことに由来します。
教育情報化推進研究会は2020年4月1日に情報学教育研究会と統合したことにより,教育情報化推進研究会は発展的に解消することになりました。
以来,情報学教育研究会は,教育情報化推進研究会が歩んできた道のりと,その理念を継承する組織として,これからの振興と学術的な発展に対し,その責務を確認する日としています。
さて,この15年あまりで,学校現場は大きく変わりました。ひとり1台の情報端末は当たり前となり,ブロードバンド環境の整備,校務の情報化の進展,そして生成AIの到来――。いずれも学びと教育に対し,新しい可能性と課題をもたらしました。
昨年の「教育情報化推進記念日」に寄せたメッセージにおいて,「教育の質の向上に資する研究開発を一層進める」と決意を新たにしましたが,その思いは本年も変わりません。
2025年,情報学教育研究会は次の重点に取り組みます。
- 授業における生成AI活用に関する研究の実装支援に向けた整備
学習到達目標と評価基準に結び付いた活用事例を収集・提示し,児童生徒の探究・協働を促す授業設計を支援するための環境を整備します。 - 校務の情報化と校務負担の適正化に向けた整備
校務にかかる時間を軽減し,児童生徒と向き合う時間の創出を目的として,校務の標準プロセスを整理し,校務負担の適正化に向けた環境を整備します。 - 情報セキュリティとデータガバナンス
事故ゼロを目指すだけでなく,発生時の被害最小化と回復力を高める「レジリエンス重視」の運用モデルを整備し,個人情報の適正管理と学習データ活用の両立を図ります。 - 誰ひとり取り残さない学びの保障
ICT活用と,アクセシビリティやユニバーサルデザインを前提に,誰ひとり取り残されない学びの環境についての研究開発を進めます。 - 知の循環を生む発信
刊行物・Webサイトなどを通じて,理論と実践を往還させる成果の可視化を進めます。
教育の情報化は,機器の更新やツールの導入で完結するものではありません。児童生徒一人ひとりの成長を中心に据え,教職員と学校組織が学び続ける文化を育てる営みです。
教育情報化推進記念日にあたり,私たちは,学校・家庭・地域・産業界と手を携え,安全で,創造的で,持続可能な学びの基盤づくりに一層尽力して参ります。
引き続き,みなさまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2025年7月29日
情報学教育研究会
代表 横山 成彦